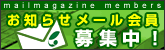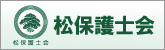HOME > 講座・研究会 > 樹木と緑化の総合技術講座 > 概要(前期) > 講義風景3
 |
平成21年度講義風景<3>
樹木の主な病害と対策
講師:窪野 高徳(森林総合研究所微生物研究領域長)※平成22年度の講師は田端雅進氏
病気とは
播き付けられた種子、あるいは挿し付けられた挿し穂が、正常に発芽・発根して育ち、緑地に植栽されてからも年々樹幹を緑に保って順調に生育し、また開花・結実していれば、その苗木あるいは樹木は健全であるといえよう。ところが、この健全な樹木が何らかの原因によって、色調・形態あるいは生育状態に外見的な異常を現したとき、これを病気という。昆虫の食害や強風などによる機械的損傷は障害といって、病気とは区別される。
病気により栽培・利用上の目的が損なわれたとき、すなわち経済的あるいは観賞的価値を減じたとき、これを被害といい、病気による被害を病害という。つまり病気は樹木の側にたった言葉であり、病害は樹木を利用する人間の側からみた言葉である。
次いで、病気の原因、病気の成立、発生誘引、病気の伝播、病原体の越冬・越夏、診断の要点、防除対策などについて解説。
 |
 |
緑化樹木の腐朽病害
講師:阿部 恭久(日本大学生物資源科学部教授)
1 腐朽病害について
樹木の腐朽病害は、生きている樹木の死んだ組織が分解されるので、基本的には枯死木、倒木、用材などの腐朽と同じ現象である。腐朽病害は生立木腐朽、あるいは材質腐朽病などとも呼ばれる。腐朽病害では、被害がかなり進行しても樹木の生死や樹勢には直接影響が現れないことが多い。腐朽病害で問題となるのは、腐朽の進行によって幹や根株の強度が低下し、地上部を支えきれなくなって幹折れや根倒れを起こすような場合である。
次いで、原因、感染経路、発生と環境、発生する部位、早期発見と対策について解説する。
 |
 |
樹木の主な虫害と対策
講師:牧野 俊一(森林総合研究所森林昆虫研究領域長)
公園、庭園などに植えられている樹木の葉が変色したり、枝、幹部から樹液や木屑が排出され、樹木の異常に気づいたときは、その原因は虫害か、病害か、生理的障害か、それともこれらの複合害によるものかを明らかにする必要がある。この原因が虫害である場合は、その害虫の名前(種の同定という)を明らかにし、それに基づき害虫の生態を知ることにより、適切な防除法を探すことになる。
ここで対象とする緑化樹木は種類が多く、そのため、これらに寄生する害虫の種類も多様である。これらは昆虫綱やクモ形綱などの広範囲にわたり、多く目(もく)<分類学上の単位>におよぶことから、種名の同定は容易ではない。害虫の種名を同定するための各分野の文献を調べ、形態上の特徴などから種の比較検討をすることになる。また、必要に応じて専門家に依頼しなければならない場合もある。
次いで、食葉性害虫、穿孔性害虫、吸収性害虫、虫こぶ形成害虫、樹木のストレス、虫害診断と対策について解説。
 |
 |